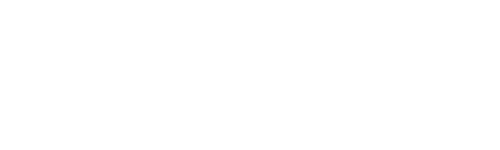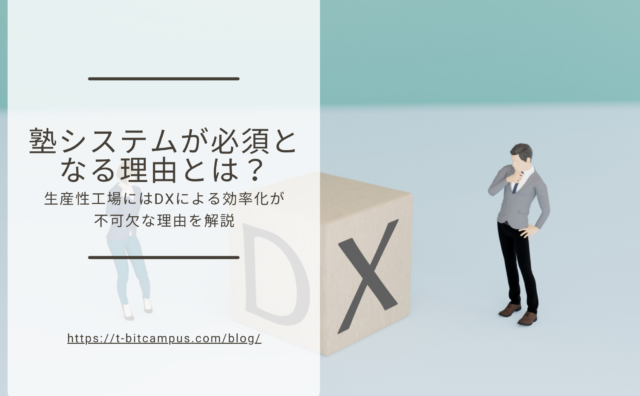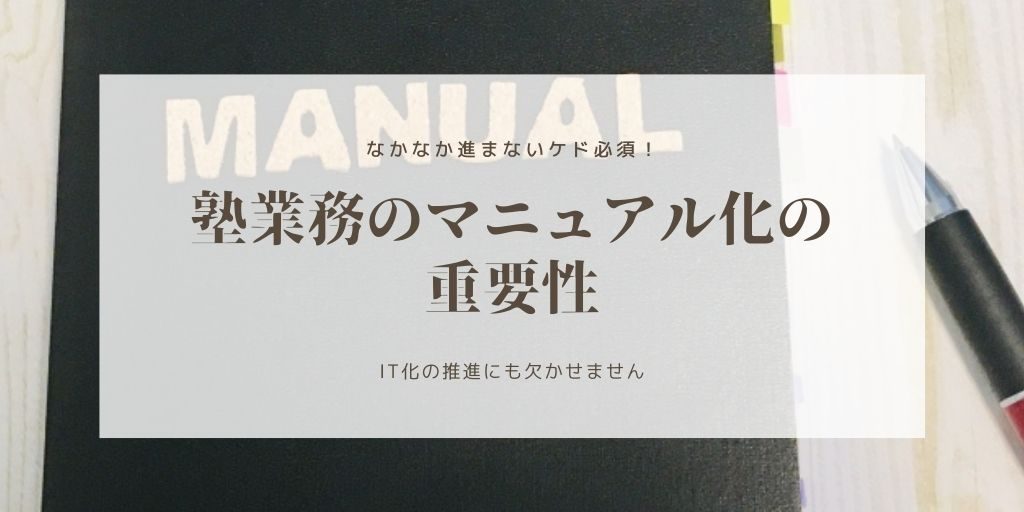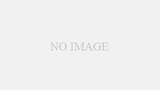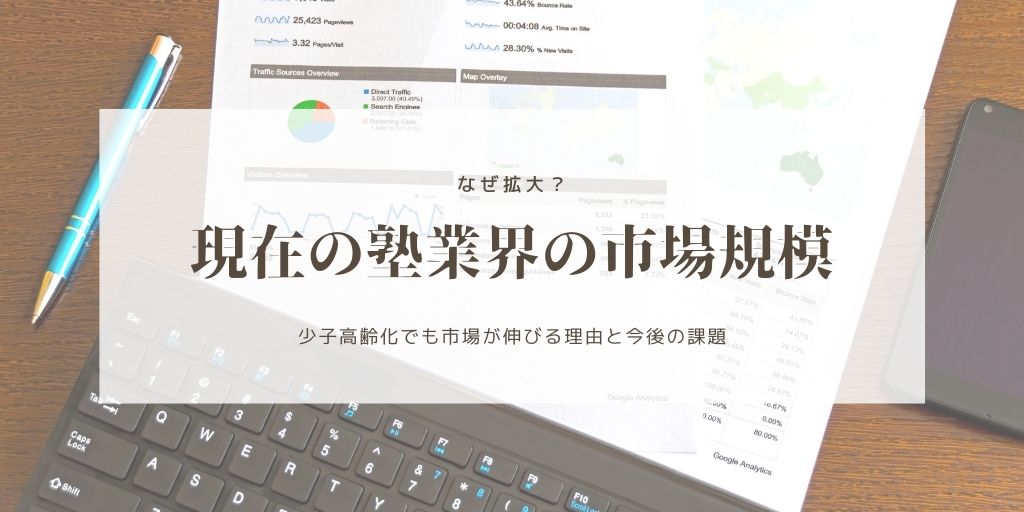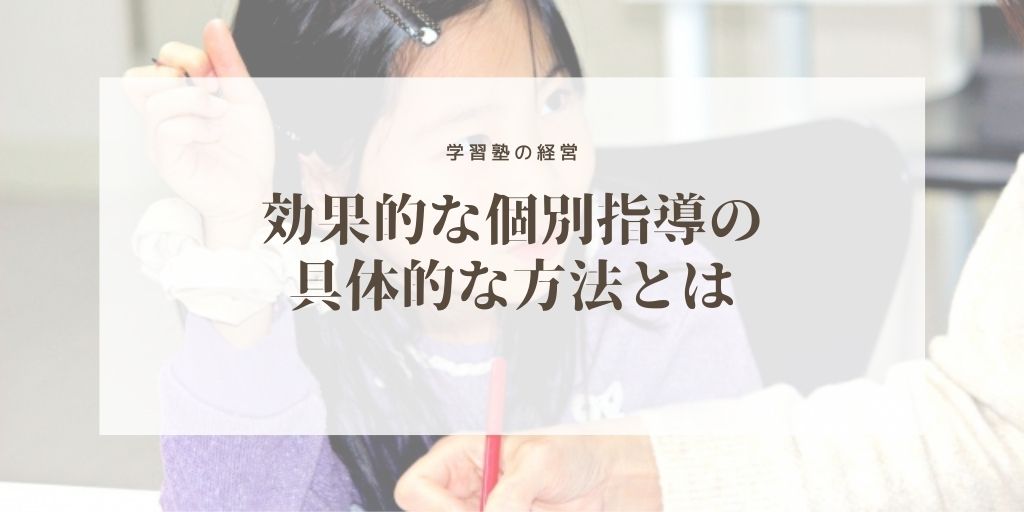塾講師が携わる業務は多岐に渡ります。
塾講師=現場での授業だけでは企業として成立しません。
塾講師とアルバイトでは業務量が違いますが、そのことを理解して入社する方は少ないでしょう。
授業ができるようになるだけでも大変ですが、塾の業務をこなせるようになるにはかなりの時間が必要です。
そのため新入社員でも即戦力として働けるように、塾業務のマニュアル化は避けては通れません。
ここではマニュアル整備ポイントやマニュアル化のメリット、IT化に向けてのポイントについてご紹介します。
働き方改革が重要視される現代だからこそ、まずは業務のマニュアル化を推し進めて、社員が長く勤められる体系を整えましょう。
\ビットキャンパスの詳細はこちら/

マニュアルが未整備のまま通じるのは事業の創業期だけ

マニュアルなしで業務が円滑に回るのは、起業直後の創業期だけです。
今後の展開を考えた場合、教室を増やしていくとその分雇用が必要となります。
その際、単一教室でできていたことがうまくできなくなっていくのです。
起業初期の少数精鋭状態ですが、組織が拡大するにつれて経験の少ない若手に権限を移譲し仕事を任せなければなりません。
しかし経験が足りない以上、ベテラン並みの仕事を求めるのは酷というものです。
ポイントは下記の2点。
- 小規模な組織では個人の能力だけで通用する
- 組織が拡大すると個人の能力だけでは通用しなくなる
目の前だけでなく、長期間での事業展開を見据えて、できるだけ早い段階からマニュアル化を図るようにしましょう。
小規模な組織では個人の能力だけで通用する
企業規模が小さい場合、少数の優秀な社員だけに管理を任せるだけで運営が成り立つケースは多いです。
多くの場合は塾長に該当するのではないのでしょうか。
もしくは中堅で塾の業務に理解の深い人材の場合もあります。
個人の能力が高い社員は、精力的に動けるだけでなく、視野も広く問題解決力も高いです。
規模が小さい場合は生徒数も少ないので、十分1人で全体を管理できるのです。
このような状況では、個人の能力が高い人材に権限を移譲して任せ、その人材をサポートをできるスタッフを増やす事が効率のよい運営のための秘訣です。
しかし、これで通用するのは創業期だけである場合がほとんどです。
規模が大きくなればなるほど、管理できるキャパを超えてしまうのです。
企業として進むべき未来を見据えて、個人の能力に頼るのではなく組織として運営できる体制を整えましょう。
どのような企業であっても、組織の成長とともに標準化・マニュアル化による生産性の向上が課題となる日が必ず訪れます。
組織が拡大すると個人の能力だけでは通用しなくなる
小規模な企業が拡大していく中で、必要になるのは組織をまとめられる人材の育成と仕組みづくりです。
授業はもちろん、日々の業務の中でもスタッフ同士の連携は必須となります。
こうした管理は職員が増えるほど難しくなるものですが、多くの経営者の方ならお分かりいただけるでしょう。
企業規模が大きくなればなるほど、目配りできない事が増えていくものです。
特に若手の思い込みによる認識の相違は、多くの経営者や管理者が経験すること。
組織として成長するために、こうした経営と現場のギャップをすり合わせていかなければなりません。
そのため中間管理職として、経営と現場の連結ピンとなる人材を育成が求められます。
さらに業務の標準化・マニュアル化やOJTを進めて、1人の力に頼らない体制を整えなければなりません。
>>塾の運営業務とは?講師とは違った面白さの運営・管理業務を紹介
マニュアルの未整備による弊害

マニュアルが整備されていない弊害はとても多いです。
個人の能力に頼り切った経営では、いつか限界を迎えます。
マニュアルが未整備による弊害には下記の3つが挙げられます。
- 業務の遅延
- 業務ノウハウのブラックボックス化
- 業務の属人化
業績の伸びている企業ほどマニュアルがしっかり整備されているのは、これら3つの弊害を回避し、誰でも同じ品質で業務ができる状態にするためです。
業務の遅延発生
マニュアルの未整備による問題の筆頭は業務の遅延です。
マニュアルが整備されていないと、業務の進行の早さがスタッフの能力に左右されます。
しっかり管理していれば防げる部分もありますが、想定外の業務遅延も発生することもしばしばあるでしょう。
学習塾は非常に忙しい業界のため、日々の雑務に追われているのが日常です。
定期テストや期別講習、受験講座など、イレギュラーな仕事も多くあります。
日々の仕事に追われる中で、現場の職員は目の前の仕事で手一杯となり、近視眼的になることが少なくありません。
そのような環境では、数ヶ月先を見据えて行動できる人材はなかなか生まれないでしょう。
こうした問題を解決することが標準化とマニュアル化です。
マニュアル化することで業務負担を軽減し、長期的な目線で仕事をしてもらえる環境を作らなけれななりません。
業務ノウハウのブラックボックス化
塾の業務は見た目以上に大変で難しい仕事も少なくありません。
そのため個人のスキルに依存した管理方法では、塾に不可欠なノウハウが特定の人材に依存し、ブラックボックス化してしまうことも。
ブラックボックス化させないためにも、有能な社員が持つノウハウを体系化・文章化し、標準化のうえ塾内で共有化しなければなりません。
業務を標準化し、座学やOJT、ロールプレイングを通して、いかにノウハウを共有するかが大切なのです。
個人の能力に頼った結果、ますます個人に依存した経営体質となり、トラブルの発生により立ち行かなくなる事態も想定できます。
業務の属人化
能力の高い人材ができる仕事は、誰にでも同様にできるものではありません。
しかし企業として存続していくためには、誰もが同じ品質で業務できることが理想です。
小規模なときは特定の人材だけができればいい仕事でも、規模が大きくなるほど人材を増やさなければなりません。
ここでマニュアルがないことが問題となるのです。
頼りにしている人材が病気にかかったり、事故にあえばどうなるかは火を見るよりも明らか。
たった1人がいないだけで業務が回らなくなる状態は脆弱な企業体質であるとしか言えません。
また業務の属人化は、特定の人材への負担を増やしているという意味でもあります。
労働環境の面からも改善するべきでしょう。
個人能力を大切にするとともに、あらゆる事態を想定し、業務の属人化を避けるためにもマニュアル整備は必須と言えます。
塾業務をマニュアル化するメリット

円滑な業務が行われれば、現場での指導もよりよいものとなります。
それは塾講師の残業の多くは、現場の指導によるものではなく、塾内の業務によるものだからです。
今後、働き方改革に対応することは、企業として避けては通れない道でしょう。
そのためには業務をマニュアル化し、労働環境を整備しなければなりません。
塾業務のマニュアル化によるメリットは下記の3つ。
- 業務が円滑になる
- 業務ノウハウの共有ができる
- 誰でもできる業務が増える
どれも社員の労働環境改善に大きな影響を与えるため、早期に整備するようにしましょう。
メリット①業務が円滑になる
マニュアルによる最大のメリットはミスの削減です。
個人の力量にあまり左右されず、一定以上の水準で業務が実行できます。
そのため複雑な処理が必要な業務ほど、マニュアル化の恩恵を受けやすいと言えます。
どのように業務を進めるかが具体化されているため、習熟化が促進されやすく円滑に進みます。
そしてマニュアル化は業務の遂行だけでなく、チェックもしやすくなるのです。
マニュアルに沿って行われているため、最終的なアウトプットの確認だけで済みます。
もちろんマニュアルは完璧ではないため、進め方において指導は必要ですが、大きな時間削減に繋がるでしょう。
それでも特定の工程や人でスタックしてしまい、業務がストップしてしまうのは十分あり得ます。
ですがマニュアル化されているかいないかで、組織の生産性はおどろくほど差が出るでしょう。
メリット②業務ノウハウを共有化可能に
塾の業務は専門的な部分はありますが、一般的な業務にも応用が効くケースがあります。
- 成績データのまとめ
- カリキュラムの一覧化
- 塾内テストの結果表示
こうした作業はExcelなどの表計算ソフトを用いて行うことが多いでしょう。
仕事の遅い職員は、仕事毎にやり方を変える場合が多いことをご存知でしょうか。
こうした繰り返しの事務処理について標準化し、マニュアル化することで、会社内で業務の習熟が進み、ミスを軽減するとともに時間の短縮にもつながります。
組織として業務の標準化を推進することは、必ず進めるべきと言えるでしょう。
メリット③誰でも業務が可能に
マニュアル化により誰でも同じ品質の業務ができれば、強い組織となるでしょう。
誰もができるような業務マニュアルを整備すれば、管理者も確認作業が簡略化され、より重要な意思決定に集中できます。
- 研修内容の精査
- 新規教材作成
- 戦略、構想を考える
こうした重要な業務へ時間を費やせるのです。
日本の企業が生産性が低いと言われる原因は、目の前の業務に忙殺され、より重要な意思決定に時間を割くことができないためとも言われています。
グレシャムの法則とも言われるこの状態からの脱却は、日本社会全体の課題でもあります。
塾業務のマニュアル化はIT化の第一歩

塾業務のマニュアル化は現状の業務状態を大きく変え、業務環境を改善します。
しかしこれからの時代、現状からのわずかな変化だけでは、時代に取り残されてしまうでしょう。
最終的に目指すべきところは、塾業務のIT化や自動化です。
古くからの慣習を大切にするのも大切ですが、現代の技術と融合させ、職員にも顧客にもよりよいサービスを提供していかなければなりません。
IT化による恩恵は、システムを触らなければ理解できない程の効率化をもたらします。
そしてIT化には、導入前に必ず標準化とマニュアルの整備が必要です。
すぐにIT化しなくとも、いつでもシステム導入ができるようマニュアルを整備しておくのは、企業にとって重要な課題です。
IT化には標準化とマニュアル化が必須
IT化を行うためには、最初に業務の標準化とマニュアル化が不可欠です。
標準化の程度でIT導入のスピードは異なります。
標準化をしなければ、そもそも業務フローが統一化されていないということ。
標準化・マニュアル化しないままIT化を進めると下記のような問題が発生します。
- システムを入れても社員が使いこなせない
- 自社にあったシステムがわからない
- IT移行期間中の業務に支障が出る
ライバル塾のIT化の噂を聞き、慌てて無理にIT化すれば必ず失敗するでしょう。
まずは自社で業務の標準化を図り、タイミングを見て自社の業務フローに合わせられるシステムを選ぶこと。
これが失敗しないIT化のためのポイントです。
あるいは全く反対に、システム側に自社の業務フローを合わせるベストプラクティスという考え方も有効かもしれません。
他の塾で成功した手法をシステムに置き換えることになるため、自社の業務フローの革命的な変革となる可能性もあります。
標準化さえ整備できていればIT化は円滑
各々の塾に最適なシステムを選ぶケース、自社でシステム開発をするケース、どちらの場合でも現状の業務を標準化しておかなければ、最適なシステムの導入はできないでしょう。
システムは導入してから変更するのは非常に難しいです。
そのため、導入前にしっかりと見極める必要があります。
逆に言うならば、標準化を進めてマニュアル化されていれば、最適なシステムも見つけやすいことからIT化は円滑に行えます。
目の前の業務効率化に加え、先を見据えて、あらゆる業務のマニュアル化を図るようにしましょう。
守破離の意識づけも企業発展には必要
人材育成の観点から、守破離を意識させることは企業発展に必要です。
業務にはいろんなやり方がありますが、まずは組織のやり方に従ってもらうことから始めてもらう必要があるでしょう。
入社当初から個の能力に委ねてしまっていては、人材は育ちませんし長くは続きません。
特に新卒での採用後、3年で離職してしまうと言われるほど離職率が高い業種です。
こうした問題を防止するために、働きやすい環境の整備も不可欠です。
そのためにも、マニュアルは必ずなくてはならないのです。
>>塾の事務作業をシステム化して生産性向上!効率化と労働環境を実現
まとめ

塾業の標準化とマニュアル化によるメリットは非常に大きいです。
業務フローを細分化し、標準化することで様々なメリットがあることはお伝えできたと思います。
- 業務負担を軽減できる
- 誰でもできる体制により離職の恐怖が低まる
- IT化を円滑に推進できる
労働人口は減少しますが、塾へのニーズは高まりを見せており、生き残りのためには激しい競争の中で差別化を図らなければなりません。
激化する塾業界での競争で勝ち残るためにも、まずは自社の仕事のあるべき姿の見直しを行い、IT化を考えてみてもよいのかもしれませんね。
>>ビットキャンパスとは?塾が開発した塾のためのシステムをやさしく解説
\ビットキャンパスの詳細はこちら/