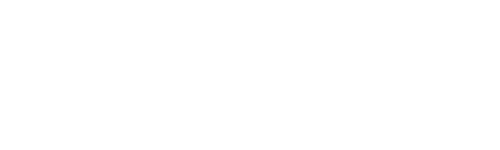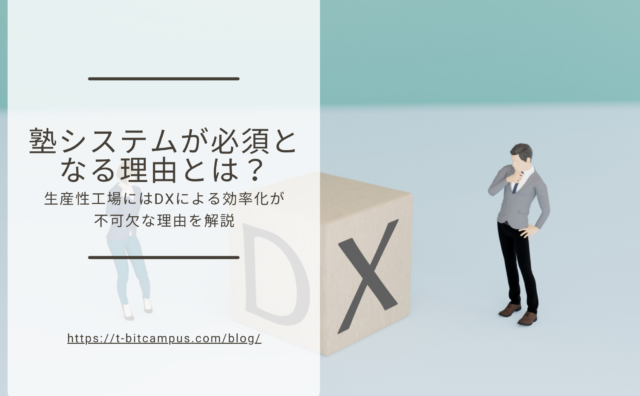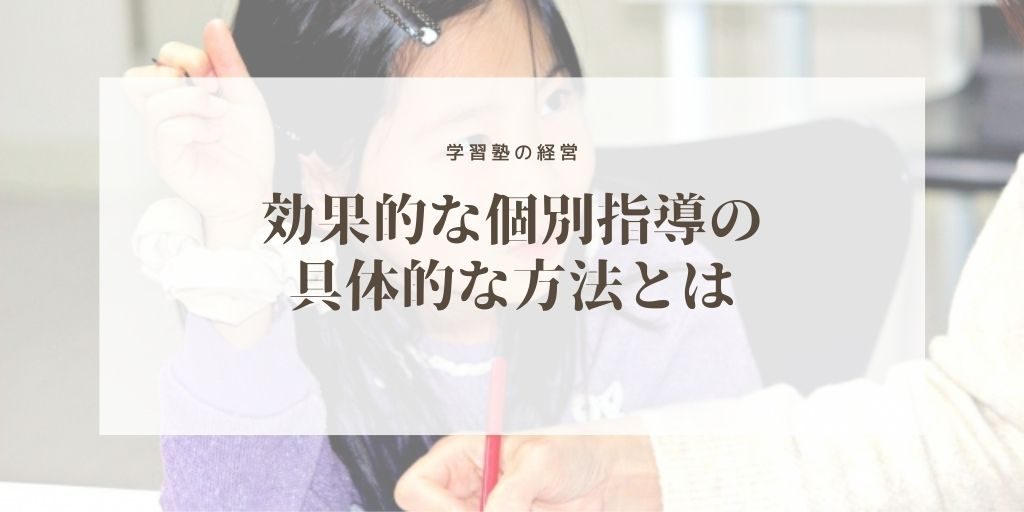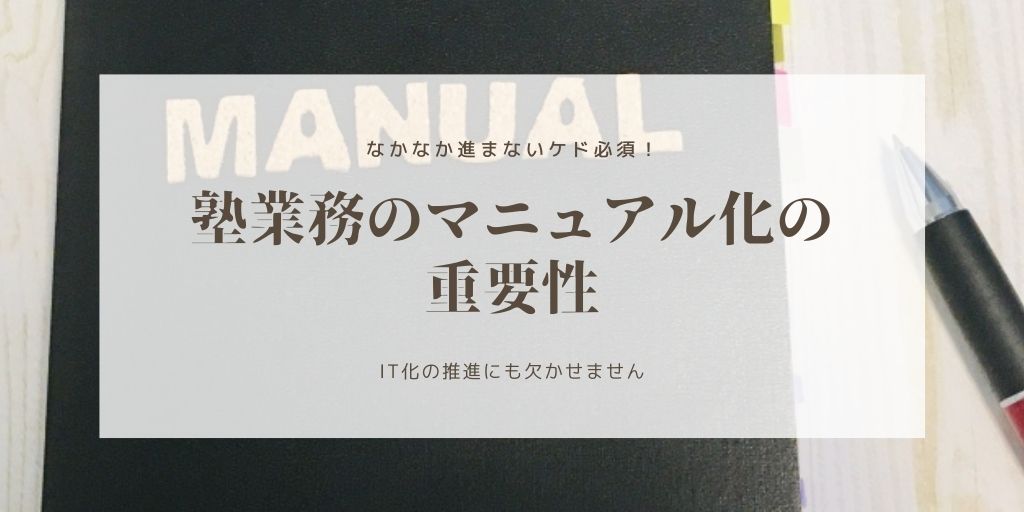これから個別指導塾を開業する場合、指導方法の問題で悩むことが多いでしょう。
1対1の指導形態できめ細かく生徒を見ていきたいと思う一方、講師の採用でうまくいかないことがあります。
学習習慣がなく、学力が低い生徒が集まって労力ばかりかかり、生徒数を増やすことができないと悩む経営者も多く見てきました。
そこで今回は、個別指導塾開業にあたり、塾の管理面から考える個別指導のやり方・方法についてご紹介します。
塾での個別指導のコツ① まず信頼関係を作る

個別指導塾では、信頼関係を築くことが非常に重要です。
当然のことと思われがちですが、実際の経営が始まると、信頼関係の重要性について真剣に考える人は意外に少ないものです。
まずは個別指導塾を開業する際に、なぜ生徒や保護者との信頼関係が必要になるのかを考えてみます。
信頼関係がないと続かない
個別指導塾の場合は、集団塾に比べてより強固な信頼関係が求められます。
集団授業の塾に比べ、先生と生徒が接する時間が長くなるからですが、単に接する時間が長くなるから信頼関係が強固になるわけではありません。
むしろ、接する時間が長いからこそ本物の信頼関係が求められます。
個別指導だからといって、生徒がわからないところを一つ一つ丁寧に教えていたら、自分で考える癖がつかず、成績が上がりません。
よく生徒が言うことですが、「塾で先生に教えてもらうとよくわかるけど、家に帰って勉強するとわからなくなる」という状態です。
だからと言って、生徒が「先生これわからないから教えて?」と質問してきた時に「自分で考えろ」と突き放すと逆効果になります。「どこまでわかったの?」と言わなければいけません。
ある程度生徒の質問に対応しながらも、肝心なところは教えず、「そこをどうしたらいいか自分で考えてごらん」と言えるかどうか、「教えない教育」ができるかどうかが重要です。
先生はわからないところを何でも教えてくれる、と生徒に評価されたら危険です。そういった”依存心”がついた生徒は成績が上がりません。
生徒の言うことを何でも聞くわけでもなく、突き放すのでもなく、厳しいけれど先生は自分のことをよく理解している、という高度な信頼関係を求められるのが個別指導塾です。
また、個別指導塾の場合は生徒のみではなく、保護者との信頼関係も重要になります。
小学生は、塾でどのような勉強をしたのか忘れてしまったり、保護者に対してうまく説明できない子も多くなります。
中学生は思春期に入り、保護者が子どもに「今日の塾はどうだった?」と尋ねても、「べつに」とか「ふつう」とかしか答えてくれません。
一方、塾で先生に叱られたとか、疲れているのに宿題をたくさん出されたとか、嫌なことがあった時だけ、子どもはきめ細かく塾での出来事を保護者に話すのです。
保護者にとって、家計をやりくりして塾代を工面しているのに、子どもが「もう塾に行きたくない!」と家で騒ぐ時ほど嫌なことはありません。
保護者には塾での我が子の様子がわからないのですから、保護者の信頼を得るためには、様子がわかるようなサービスをしなければいけません。
手厚い定期的な保護者面談や、授業ごとの授業報告、保護者会が必要になります。
特に生徒が増えている塾ほど、保護者面談時間を多くとっています。勉強や入試のことだけでなく、教育に不熱心な夫への愚痴や、近所の噂話まで聞くことに時間を割いています。
そこまで信頼関係を築いて初めて、何かあった時でも「あの先生なら何か意図があってそうしたはず」と味方になってくれますし、長く通塾してくれるようになります。
気を遣うことも多く大変ではありますが、その反面、保護者との信頼関係を築ければ大きなリターンもあります。兄弟も塾に通わせてくれるようになりますし、大学受験までずっとお願いされることもあるでしょう。長期的な関係を築ける可能性が高くなるのです。
信頼関係をどう築くかというのは、奥が深いものです。生徒だけでなく保護者にも、意識して信頼を得られるような努力を心掛けましょう。
決して否定をせず話を聞いてあげる(傾聴する)
生徒と信頼関係を築く際には、否定しないで話を聞くということも非常に重要です。
特に小学生の場合は、先生に否定されることで自信をなくし、塾に通うのが嫌になってしまうことも多いので注意しましょう。
厄介なのは、「知らないうちに否定している」ケースです。
よくあるのが採点時の丸つけです。丸つけの際に×をつけられることが嫌いな生徒は意外に多いのです。
対処方法としては、赤と青の2種類のペンを用意します。最初の丸つけは赤のペンで行い、間違っていたところは×をつけないで生徒にもう一度解説をしながら解かせます。
最後に正解できた時に、青で丸つけをすれば、生徒の自尊心も傷つきませんし、間違った問題かどうかもわかります。
また、「前も説明したよな?」と言ってしまう時のような、何気ない言葉遣いにも注意しましょう。これも否定されたように感じてしまい、次から二度と質問してこなくなります。
どのようなケースでも、生徒が話しかけてきたら言葉を発する前に「傾聴する」ことが大切です。生徒の話をよく聞いた上で発言すれば、否定されたとは思われないものです。
生徒の話をよく聴くことを心掛けましょう。
>>塾に寄せられるクレームの原因と対応方法とは?クレームから学ぶ
塾での個別指導のコツ② 生徒に合わせつつペースを保つ

個別指導塾では、生徒のペースに合わせて授業を行うことも重要です。
個別指導塾に入塾してくる生徒は、集団指導塾についていけずに勉強がわからなくなった子や、逆に勉強がよくできて、集団指導塾では授業スピードが遅いと考えている生徒も少なくありません。
そのため、そのような生徒の要望を理解せず、カリキュラムがあるからと一定のペースで授業を行ってしまうと、個別指導塾に通う意義を感じなくなる生徒や保護者は多いのです。
個別指導塾に何を求められているのかを明確に理解しましょう。
生徒によって苦手箇所やわからないポイントは千差万別
二人として同じ生徒はいません。生徒ごとにわからないポイントは違いますし、学習や理解のスピードも異なります。
先生にとっては、同じことを何度も説明したり、やることがたくさんあるのにゆっくり時間をかけて指導するのはストレスが溜まることでしょう。それでも、生徒がつまづいている時は、忍耐強く、ゆっくり教える努力が必要です。
個別指導形態を維持しながら、講師の数が少なくても、生徒のペースに合わせた指導をしていきたい場合、AIデジタル教材を導入するのもいいでしょう。
AIデジタル教材であれば、生徒一人ひとりの理解度や学習習慣に合わせて問題や解説を変えてくれます。解答が間違っていれば、どの単元の理解が不十分なのかをすばやく分析し、必要であれば、学年を遡って理解が不十分な単元を学習させてくれます。
一人ひとりの生徒を個別に丁寧に見ていく個別指導塾は、カリキュラムを生徒に合わせて変更できない集団指導塾の弱点を補えるよう、より付加価値が高い取り組みが必要になります。
生徒個人を尊重しながらペースも守る
個別指導塾では、基本的には生徒のペースで授業を進めていくことが重要です。
とは言え、学年で学ぶ範囲が決まっていますから、授業計画を無視するわけにもいきません。授業計画では、どの時期に何を行うのかを、生徒の同意を得ながら明確にすることが必要です。
特に受験学年の場合は計画が重要になるので、生徒の学習ペースを考慮しながらも、綿密な授業計画に沿った授業が求められます。
塾での個別指導のコツ③ スキルだけに依存しない仕組みを作る

個別指導塾の場合は、指導方法やコミュニケーションスキルがとても重要です。
実はこの点こそが、特に講師経験もある経営者にとって、開業して最初に直面する課題でもあるのです。
学生時代にアルバイト講師を経験している経営者は、指導に対してはある程度のスキルを持っています。
しかし、自分の努力で身につけた言わば「暗黙知」を、マニュアルなど目に見える形に「形式知」化できたとしても、経営者と同じように他の講師も振舞えるかどうかはわかりません。「ナレッジマネジメント」は、とても難しいものです。
講師によって持ち合わせているスキルや知識も異なりますので、その点を考慮した仕組み作りが必要になります。
属人的な指導には限界がある
他のサービス業界と比較すると、学習塾の弱点はサービス品質が一定化しないという点にあります。講師によって授業の教え方や上手さが異なることが多いのです。
その結果、一部の優秀な講師のみを頼りに塾の経営をしなければならない状況も生まれます。
教え方が人によって異なってしまうことは、人間が教える個別指導塾では仕方のないことです。
しかし属人的な指導には限界があるのは間違いありません。実際に、一部の優秀な講師のみに頼った結果、その講師がやめたことで塾全体の評判が下がってしまったという事例もあります。
このように、属人的な指導方針は経営の面では大きなリスクを伴うのです。
誰でも一定の成果を上げられる「仕組み化」が重要
個別指導塾では、属人的な指導方法を取り続けると、リスクの高い経営を行わざるを得なくなります。
そのため、誰でも一定の成果を上げることができる「仕組み」の構築が必要です。
だれでも一定の成果を上げることができる仕組みができれば、講師が辞めただけで塾の評判が下がるというリスクを避けられます。
また、一定の成果を上げられる仕組みを構築できれば、新たに講師を雇った際の教育時間も減らせ、効率的な講師育成も可能でしょう。
新人講師を教育する期間は、短ければ短いほど経営コストの面で優れていることは言うまでもありません。
当然、未熟なうちに生徒を指導させてしまうと、トラブルや信頼関係が崩壊してしまうことにもつながります。
そのため、経営コストを抑え、授業品質を維持するためにも、新人講師が成果を出せる仕組みづくりは必要と言えます。
誰でも一定の成果を上げられる仕組み作りに重要なこと
誰でも一定の成果を上げられる仕組みを構築できれば、経営リスクを大幅に減らせます。
しかし実際は、大手塾でもない限り、指導方法の細かいマニュアルを作成したり、そのマニュアルに沿って講師が指導できているかを逐一確認したり、何度も長期に渡って研修を重ねていくことは難しいと思います。
特に個別指導塾で大学生講師を雇っている場合、講師は定期的に短期間で卒業してしまいます。時間とコストをかけて教育し、ようやく一人前に育った時に塾を離れてしまうのです。
従って、仕組みを構築するには、①業務の標準化、②人材育成の標準化、③学習指導の標準化、の3つの視点が重要になります。
一つ目の「業務の標準化」ですが、一言で言えば「ITシステム化」です。
講師によってエクセルの書式が違っていたり、講師によって集める情報が違っていたりしたのでは、その講師が卒業していなくなった時に、ノウハウも含めて全てが消失してしまいます。
また、講習会時は何百コマ、何千コマの授業を組まなければなりません。講師の勤務予定、生徒の受講希望日を組み合わせる作業が大変です。生徒一人あたり1時間程かかることもあります。
せっかく組み終わった時間割に変更や修正が入ると、同時に様々なコマや先生の予定も変更しなければいけません。講習会が始まるまで、夜も眠れない日が続くこともあります。
そうならないためには、誰が見ても同じ形式で同じ情報を間違えずに入力できる時間割作成システムを導入することで、ミスやムダ、ストレスを防ぐことができます。
二つ目の「人材育成の標準化」ですが、面白い取り組みをしている塾が参考になります。
その塾では、卒業生に講師になってもらい、大学の学年が上がる度に査定を行い、最後は一番評価の高い学生しか残さない仕組みを作っています。
生徒が高校部在籍時に「うちの塾の講師になって欲しい」と声をかけ、大学合格時から講師になってもらいます。塾の理念や考え方、先生の指導法が生徒時代に身についていますので、ある程度標準化できるのです。
また、大学卒業時に最高評価で残った学生は、卒業時に最高評価の視点で後輩を連れてきてくれます。「この後輩なら、この塾の指導方針を理解し、この塾のやり方に合った指導をしてくれるはず」という視点で人選しますから、これもある程度の標準化ができるようになります。
三つ目の「学習指導の標準化」ですが、教材や前述したAI教材を活用するものです。
教材によっては、問題ごとに難易度ランクがついている教材があり、生徒のレベルが5段階であれば、難易度ランクが5の問題だけは確実に解けないといけない、という指導ができるようになっています。そのランク以外の問題は解く段階にないことが、新人講師でも容易にわかりますので、これも標準化につながります。
AI教材については前述した通りです。講師ではなくAIがデータに基づいて指導しますので、属人化を防ぐことができ、生徒は誰でもいつでも同じ水準で授業を受けることができます。
このような取り組みを実現することで、個別指導塾のサービス品質の標準化を図りましょう。
塾での個別指導のコツ まとめ

塾で個別指導をおこなう際には多くのコツがあります。
・集団指導塾にはできない生徒のペースに合わせた授業
・生徒・保護者との強固な信頼関係の構築
・誰でも成果を出すことができる標準化された指導方法の構築
上記の3つのポイントを抑えることで、塾経営をしたことがない人でも収益を出すことができる個別指導塾を経営することが可能です。
>>学習塾にIT化が不可欠な理由とは?遅れるほど差がつくIT化
\ビットキャンパスの詳細はこちら/