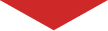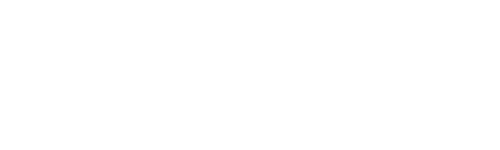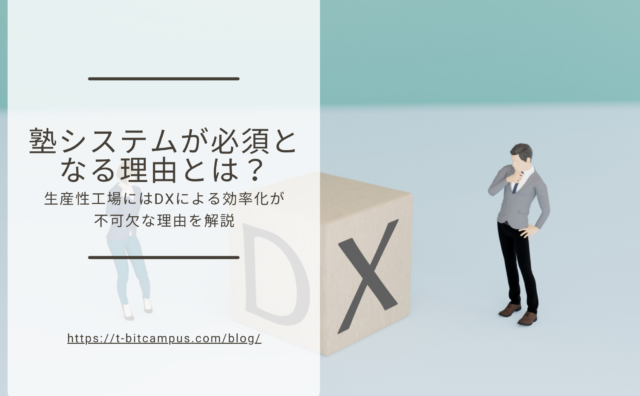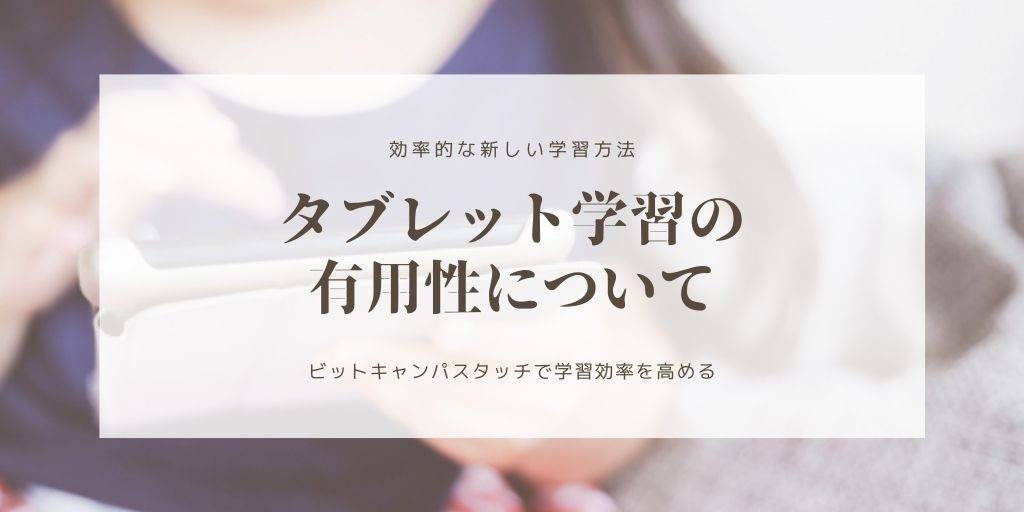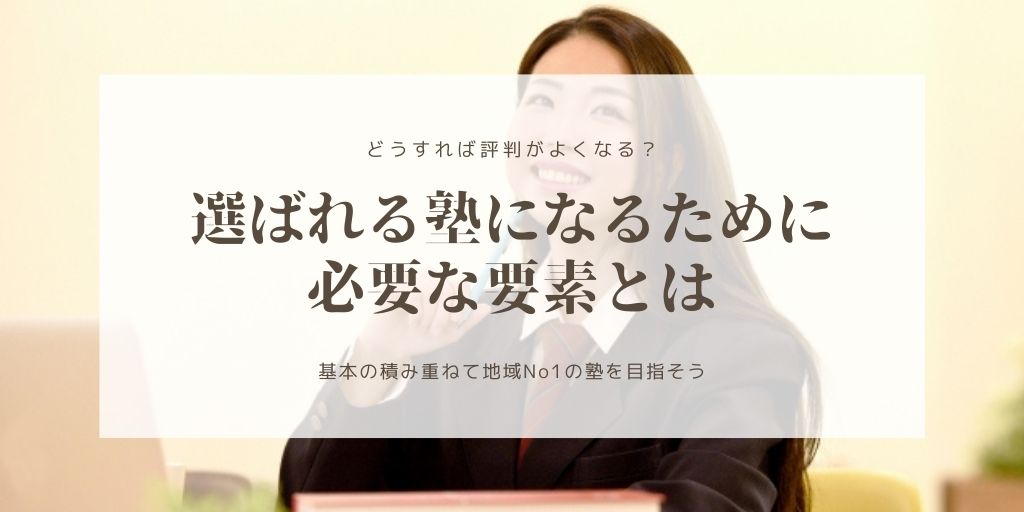一足先にタブレット学習を取り入れる塾が増えつつある中、公教育の現場でもICT教育にようやく本腰を入れ始めました。
「先生と生徒がフェイスtoフェイスで教えるのにこだわりたい」
「生徒とのコミュニケーションを大切にしたい」
このような理由で、IT化の波に乗らない企業は非常に厳しい戦いを強いられるでしょう。
もちろんタブレット学習にはメリットもあれば、デメリットもあります。
しかし、上手に取り入れればこれまで以上の成果が出せる事実を知っておくべきです。
今回は、塾がタブレット学習を取り入れるメリットやデメリット、意義についてご紹介します。
一昔前とは大きく変化したタブレット教育について、自社に取り入れたらどうなるのか、というイメージを持つきっかけになれば幸いです。
\ビットキャンパスの詳細はこちら/

タブレット学習とは?おすすめする理由を紹介

タブレット学習は、ただ問題が次々に出題され、淡々と解くという退屈なものではありません。
タブレットを利用した学習のポイントは以下の2つです。
- 今までにない新しい学習方法ができる
- 紙媒体ではできない仕組みが多くある
それでは、1つずつご紹介します。
タブレットを利用した新しい学習方法
以前のタブレット学習といえばこんな物をイメージしませんか?
- 問題が出題されるだけ
- 〇×だけ(あっても軽い解説のみ)
実際に過去の物は、問題集をタブレットで解くだけの紙媒体の代替、でしかないという点がデメリットでした。
魅力を感じる一方で、現場の講師との触れ合いを望む生徒・保護者も多く、思うように需要が伸びないため、塾にとって脅威ではないと考える経営者も多かったのではないでしょうか。
しかし、現在はタブレット教材も大きく変化しています。
- レベルに合わせた問題選択
- 映像授業の増加
- 自分のペースで理解を深められる
このように過去と比べるとかなりの進化を遂げ、能動的な学習方法になったため、ケースによっては授業よりも効果の高いものになっています。
- カリキュラム作成
- 学力状態の把握
- 苦手部分への細やかな対応
このような学習への応用が、タブレット1つでできるようになりました。
このタブレット学習は、集団指導から個別指導へと時代が変わったとことと同じ流れではありません。
タブレット学習は公教育でも取り入れる動きが活発になっています。
つまり、塾業界だけでなく、教育のスタンダードになりつつある学習方法なのです。
紙媒体では実現できない仕組みが数多く存在
紙媒体での手間の多くをなくせるのがタブレット学習です。
紙媒体の場合、問題数を増やせば増やすほど分厚く持ち歩きや利便性の劣る教材になってしまいます。
生徒のレベルに合わせて指導をする場合、やるところとやらないところが出てしまうため、使われないページも多く出てきてしまうでしょう。
そのため保護者の目にも「きちんとやっていない」と見られるケースもあるかもしれません。
これらのデメリットもタブレット学習であれば改善します。
- 必要な問題だけチョイスができる
- 学習データが見られ、保護者にとっても安心
また学習内容もデータとして記録できるため、保護者がいつでも見たいときにすぐ確認できます。
さらに豊富な映像授業や類似問題検索により繰り返し学習ができるなど、学力向上に繋がるコンテンツも多いです。
塾でのタブレット学習のメリット・効果

タブレット学習のメリットや効果はたくさんありますが、中でも以下の3つが子供の学習に良い点です。
- ゲーム感覚で学習できる
- 進捗状況の把握ができる
- 繰り返し学習により苦手問題の克服ができる
どれも広い層からのニーズがあるものなので、1つ1つを把握しておきましょう。
メリット①ゲーム感覚で学習できる
子供にとって勉強は嫌なもの、ゲームは楽しいもの。
楽しみながら学習するシステムが満載なタブレット学習では、ゲーム感覚での学習が可能。
そのため、机に向かうハードルをぐっと下げられます。
子供にとって、ゲーム感覚での学習はとっつきやすいです。
- 勉強が苦手
- 学校の授業についていけない
- 人と話すのが苦手
こうした特性を持った子供でも、すんなり勉強に入られる点は大きなメリットでしょう。
また勉強が得意な子でもゲーム好きな子は多いです。
自分のレベルがどんどん上がっていくのが実感でき、勉強が楽しくなる仕組みが組み込まれています。
特に勉強が得意な場合、自分の課題を理解している生徒が多いので、勉強時間が伸びるのは大きなメリットです。
メリット②学習の進捗状況を自分で確認できる
現在のタブレット学習は、問題を解き進め、解説を聞き、演習をするのが1タームです。
これを繰り返すと、得意分野・苦手分野がはっきりするため、何をどれだけ勉強すればいいのかが明確になります。
- ひっかかりやすい問題
- 自分のミスの傾向
こうした傾向を把握できるため、テストでの得点力の向上に繋がりやすいです。
またこれらがデータとして活用できるのが良い点ですよね。
これにより、テスト前に苦手な部分の総復習がしやすくなるため、勉強が苦手な子でも効率的な学習が可能です。
さらに、カリキュラムがステップ形式で見える化されています。
- 自分が今、どの位置にいるのか
- あとどれだけの内容があるのか
このような事が明確となり、ゴールへの見通しが立つのがメリットです。
終わりが見えていれば、勉強のモチベーションの増加にも繋がります。
メリット③繰り返し学習で苦手問題を克服できる
「できない」「わからない」から「できる」へは、とても大きなハードルがあります。
特に、テストで思うように結果が出ない子は以下のような状態に置かれていることが多いです。
- 過去にやった内容なのに解き方を忘れている
- 間違った解法を覚えてしまっている
- 「できる」の信号が早期に送られ、反復しない
小中高での勉強は突き詰めると最後は暗記ですよね。
理解力が高くても完全に暗記していなければ得点力には繋がりません。
理数系でも文系でも本質は同じです。
できるだけ多くのことを覚えられる状態を作られるかがポイントでしょう。
そのためには、記憶の定着を促す繰り返し学習が欠かせません。
スポーツでも、ただ教えてもらっただけでできるようにはなりません。
同じことを何度も繰り返して、自分の体の使い方を覚え、そして反射的にできるようになるのです。
究極的には勉強もスポーツと同じで、苦手だからできないのではなく、繰り返しの量が足りないのです。
しかし子供は同じ内容の繰り返しや反復がつまらないため、なかなか続かないもの。
タブレット学習では、様々なコンテンツ、豊富な問題量で生徒のモチベーションを上げてくれるのです。
「勉強をやりなさい」と言わなくてもやりたくなり、自然と繰り返し学習ができるタブレット学習。
苦手克服には最適なツールだと言えるのではないでしょうか。
塾でのタブレット学習のデメリット・弊害

様々なメリットや効果のあるタブレット学習。
魅力的なコンテンツが多いですが、デメリットも忘れずに知っておきましょう。
塾としての採用を進めるためには、これらのデメリットへいかに対処するかがポイントです。
タブレット学習のデメリットには、下記の2点があります。
- 「書く作業」が減る
- 目に負担がかかるケースも
これらへの対処は生徒や保護者の抵抗をなくし、安心感を与えられるきっかけになるため対応しましょう。
デメリット①「書く作業」が減る
タブレット学習は、「書き」の時間が圧倒的に少なくなるのがデメリットです。
勉強で大切な要素は以下の通り。
- 目で見る
- 手で書く
- 声を出す
- 耳で聞く
このように五感をフルで使うことで学習効率が挙がるとされています。
この中で勉強の分野においては、アウトプットの基礎となる「書き」に関しての重要度が非常に高いです。
現在の保護者の年代では「書いて覚える」が主流の時代でした。
暗記をするにも、公式を使った演習をするのにも、とにかく「書き」がポイントと考える保護者は多いです。
実際に書くためには、脳で考える時間も必要になります。
そのため「書き」が減る=暗記がしにくくなると言えるのです。
暗記表を目で見て暗記できる子は少数しかいません。
時間をかけて、繰り返すことで記憶として定着するのです。
これを知らず「タブレット学習は最先端だから大丈夫」盲信していては、生徒の成績を大きく伸ばすことが難しくなるかもしれません。
書く作業が減るデメリットをいかになくすかが重要なのです。
タブレット学習と書く作業を組み合わせ、双方の問題を補完するのがよいでしょう。
デメリット②目に負担がかかる場合がある
タブレットの画面を直視するため、こんな問題が起こる場合もあります。
- 目が悪くなる
- 目が疲れやすくなる
特に子供は集中し始めるとずっとやり続けられるため、注意を払わなければなりません。
まばたきの回数も減るため、目薬等での対応が必須です。
またタブレット画面が発するブルーライトは、大きな問題があるとして社会的にも認知されています。
さらにエアコンなどによるドライアイ対策、花粉症などのアレルギー対策も必須です。
花粉症などのアレルギーを持つ子にとっては、長時間画面を見続けるタブレット学習は厳しいものになる恐れもあります。
保護者の中には、画面を見続けるのに不安を持つ方もいるので、自社での対策をきちんと伝えられるようにしておきましょう。
塾でのタブレット学習は採用する価値がある

メリット、デメリットを比較すると一長一短はありますが、それでも塾でのタブレット学習の採用は非常に価値が高いと言えます。
様々なコンテンツがありますが、時代の流れとしては、いかに個人に合わせられるかがポイントです。
タブレット学習と一言で表しても、様々なものがあります。
そこでタブレット学習採用のポイントは以下の2点。
- タブレット学習にはビットキャンパスタッチがよい
- 時代の流れは個別最適化
それぞれの特徴も踏まえてご紹介します。
タブレット学習にはビットキャンパスタッチがおすすめ
各社が提供するタブレット学習のシステムには、長所と短所があります。
例えばこんな問題が考えられます。
- 問題数は多いが、解説が短く定着しない
- ゲーム性は高いが、反復練習の機能がない
- 問題量は多いが、対応していないデバイスがある
いくら素晴らしいコンテンツをそろえても、成績効果が上がらなければ生徒はやめてしまいます。
タブレット学習だからこそ、現場の講師の力量で解決しづらい問題が多いです。
ビットキャンパスタッチには、現場の講師が助けられ、生徒の成績効果に繋がる仕組みが満載。
- ゲーム性を取り入れ、入りやすく工夫
- 各科目の進捗状況を見える化
- 継続しやすいコンテンツで、学習習慣が身につく
- あらゆるデバイスに対応
- 間違えた問題は、時間をおいて再度出題
- 主要教科の問題数は30,000問
こんな魅力がいっぱいです。
基礎力向上の手助けをするため、本物の学力が身に着けられます。
勉強への取り組みやすさが集中力を生み、学力定着を促してくれるでしょう。
さらには進捗も一目でわかるため、モチベーション維持もしやすいです。
タブレット学習には、講師や生徒、保護者の「ほしい」がいっぱい詰まったビットキャンパスタッチがおすすめです。
時代の流れは「個別最適化」。生徒一人ひとりに合った学習内容を提供。
一昔前は学習塾といえば、集団指導がメインでした。
その流れを一新させた個別指導は、一人ひとりに合った学習を提供するというもの。
様々な学力層の生徒に対応ができる指導形態として、非常に大きな伸びを見せました。
しかし個別指導には問題もあります。
- 学生アルバイトの指導力
- 好きな先生に見てもらえない
- 生徒のペースに合わせ過ぎて授業が進まない
これからの時代は、いかに効率よく指導を行えるかがポイントです。
それには、現場の先生に任せきりで過去のままのシステムでは対応できません。
近年のトレンドは個別最適化です。子供が持つ能力を、どこまで引き伸ばせられるかが大切なのです。
子供を伸ばすには、講師の存在はもちろん大切です。
しかし講師に任せきりではなくシステムを活用して学習を管理し、徹底的に効率化を図り、講師の力量に左右されず、最大限子供を伸ばせる時代なのです。
一人ひとりに合わせるためには、客観的なデータも必要です。
こうした面からも、タブレット学習のメリットは非常に大きいと言えます。
まとめ

教育業界のIT化の波は、今後一層大きなものになると予想されます。
公教育での採用は、時代の大きな変化を表しているのです。
これまでの先生と生徒の関係から、タブレットを上手に使った学習へと変化させ、より効率的に子供の潜在能力を引き上げる指導が必要でしょう。
タブレット学習にはメリットもあれば、デメリットもあるため、双方をきちんと理解して採用しなければなりません。
特にデメリットへの対応が生徒や保護者の満足度に直結するため、細心の注意を払いましょう。
時代の流れは一人ひとりの個性に合わせた個別最適化への適合です。
この時代の波に乗るには、現場の講師の声をベースに練り上げられたビットキャンパスタッチがおすすめです。
講師・生徒・保護者の「ほしい」がすべて詰まったタブレット学習。
タブレット学習の採用をお考えの方は、ぜひ一度目にしてみてください。