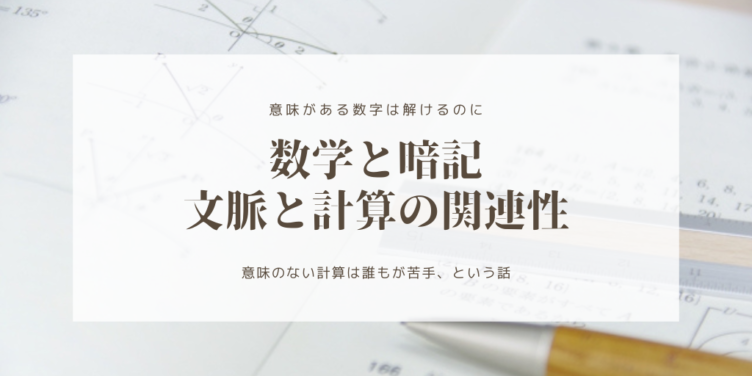 コラム
コラム 数学は暗記科目か?
2023年の入試も終わり、今年も思考力や理解力を問う傾向が続いています。入試を終えた理系の高3生に聞くと、「数学は暗記科目だと思う。入試で問題を見てパッと解法が浮かばなかったら時間内に解けない。」と言っていました。数学は暗記科目なのでしょう...
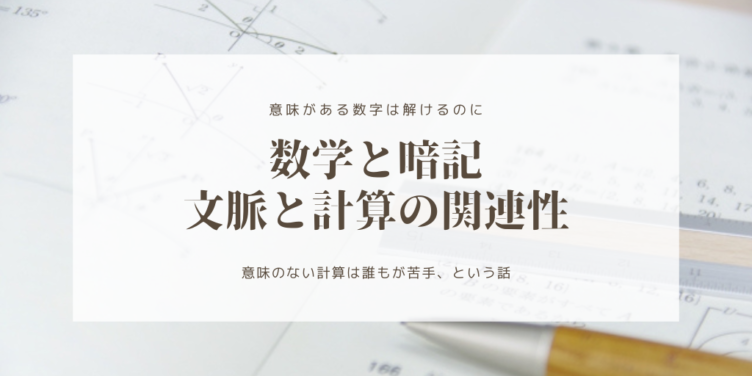 コラム
コラム  コラム
コラム  コラム
コラム  コラム
コラム 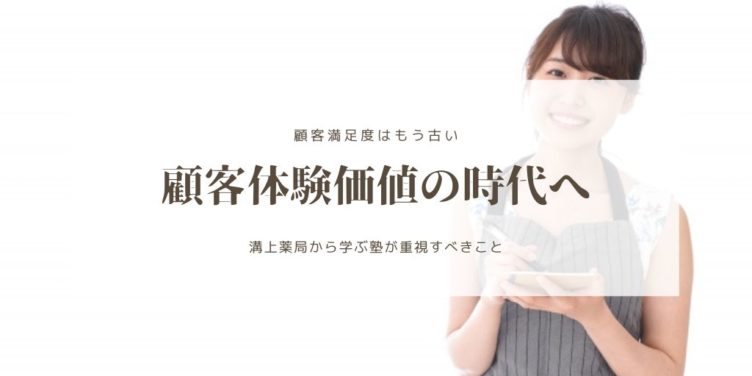 コラム
コラム 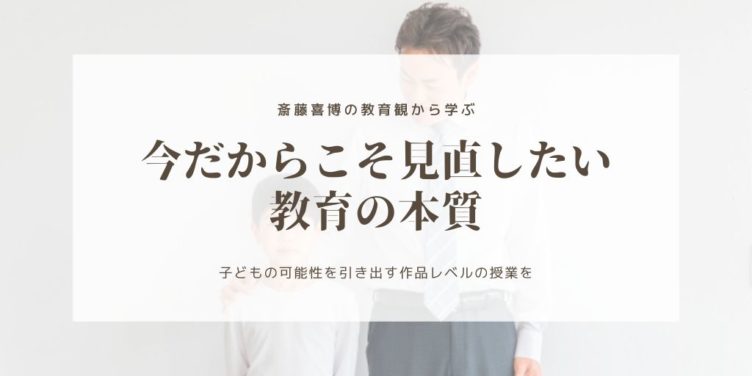 コラム
コラム 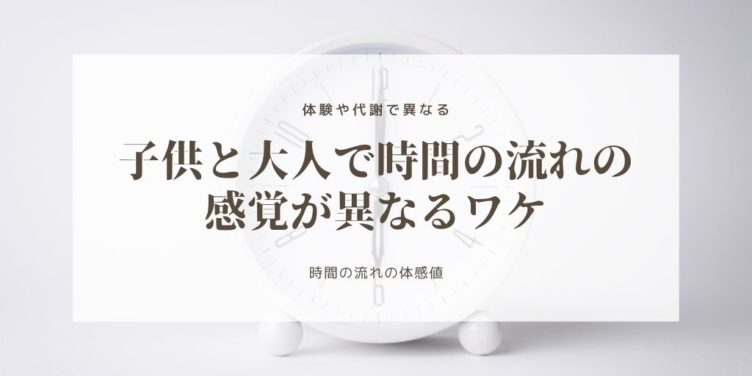 コラム
コラム 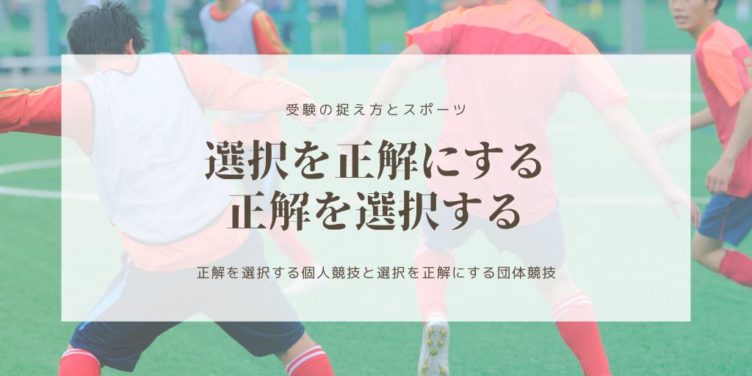 コラム
コラム 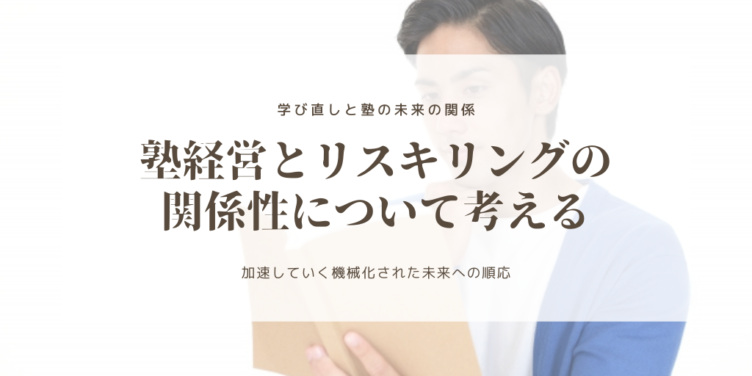 コラム
コラム 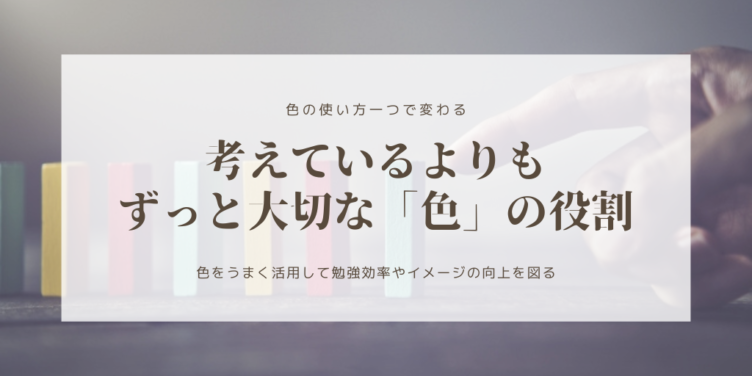 コラム
コラム